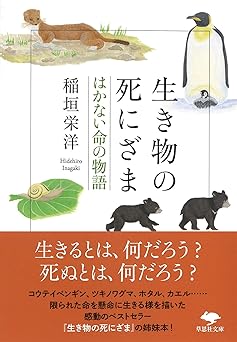|
この本は単行本の頃から何度も読みたいなと思いながらも買えずに、手にとっては置いてを繰り返してきた。最近になって文庫本になっているこちらの本に出会い、ようやく購入した。というよりも、正確には2冊目のこちらではなく『生き物の死にざま』という副書名が付かない方の版を買ったつもりがこちらを買ってしまった。しかしこんなに早くに文庫本になっていたのか…。1冊目を読んではいないのは少々残念ではあるが、しかたながない。買い間違えたのは自分だ。だが最初の本も必ず読みたい。著者が初めに書きたかったことを知りたい。
さて、今回は2冊目の本についての話だ。読んでみると各章の中にはそれぞれいくつかの生き物の名前があげられ、その生と死が淡々と書かれている。死というのは当然ながら、その生き物の生きる姿が必ず存在するのだから当然といえば当然のことである。その文章は淡々としながらもとても柔らかく、私感だが博物誌を思わせた。
生き物というのはそれぞれ生きるために、子孫を残すために、なんと面白いしくみをもっているのだろう。それはもう、私たちの力の及ばない世界だ。以前チューリップのことを調べていたときに種でできたものは元の親とは違う色の花が咲くこともあり、咲いてみるまで色はわからないという。いわばチューリップという遺伝子は受け継ぐけれど同じでない別の個体となるとあった。ところが球根だと同じ色の花の同じ遺伝子を継ぐ個体になるというのだ。何から芽を出すかによって完全一致の遺伝子になるか否かが変わるというのもとても印象的で心に残ったことだった。そしてこの本の中で樹木について書かれた箇所で木にも同じことが言えることを知った。挿し木もまったく同じ遺伝子を受け継ぐ。種なら0歳スタートだが樹齢何百年の木から挿し木になった木は一体何歳なのか?著者は考える時があるようだ。そういわれて少し自分でも考えてみるがそれを見つける必要があるのだろうか?とやめることにした。
さて、この本読み進めど読み進めど、毎回モヤモヤした気持ちが残るのだった。なんだろう?このモヤモヤの正体は?なにか満たされないような気持ちのまま読み進む。
人は生き物の際立った部分をみて生き物をイメージしている。イメージは必ずしもその生き物の全体ではない。私たちは(少なくとも私は)本当の生き物たちの姿を知らずにいるのかもしれない。例えばこうだ。チーターは他のどの動物よりも足がはやいが、はやく走れはすれど走るために特化した体は軽量で持久力はなく戦いには向かないだとか。そして誰よりも早く走れるのに狩りの成功率は40-50%という事実。ライオンが百獣の王などと言われているがチーターと比べたら狩りの成功率はさらに低かったりするらしい。生まれる子どもの数は大人になるまでの生存率が低ければ低いほど多くなる。地球上がけっして強いものばかりにならないのは、どの動物にもいろんな特性があり、そのことにより食われるもの、生き残っていくものが共存しうる仕組みの中で循環していることがわかる。
普段、生きた動物の(自然の中にいる)本来の姿に直面することは、私にはほとんどない。現場をしらない私は、野生に直面したらあっという間に命を落とすにちがいない。生きる上でもっていたほうがよい知識とはなんだろうか?自分に直接出会うであろう動物たちとの関わりによって変わってくるのかもしれない。必要に応じて知ればいいとも思う。だが、知らないことを知ることも楽しい。ただ知ったとしても机の上や本の中で知るというのと実際に知るのはやっぱり違うということを頭においておきたい。
ラストまで読み終わり、もやもやの正体について考える。もやもやの正体は自分が人間であることから生じているように思った。多くの生き物たちを自然の死ではなく不自然に死においやっているのが人間であると言葉としてじわじわと伝わってきたからだ。わかってはいても変われずにいる自分。自分に落胆していたのだった。
人もまた自分たちの仕組みの中で苦しんでいるように思う。著者は最終章を人でしめくくっている。人間とはどういう生き物なのだろうか?著者の文章にはその人間の特性(みんながよく知っている)が書かれている。未来へ先手先手を打つ私たち。「今」を生きる。その言葉の余韻は一人一人に考える余白をくれているように思った。(文:やぎ) |