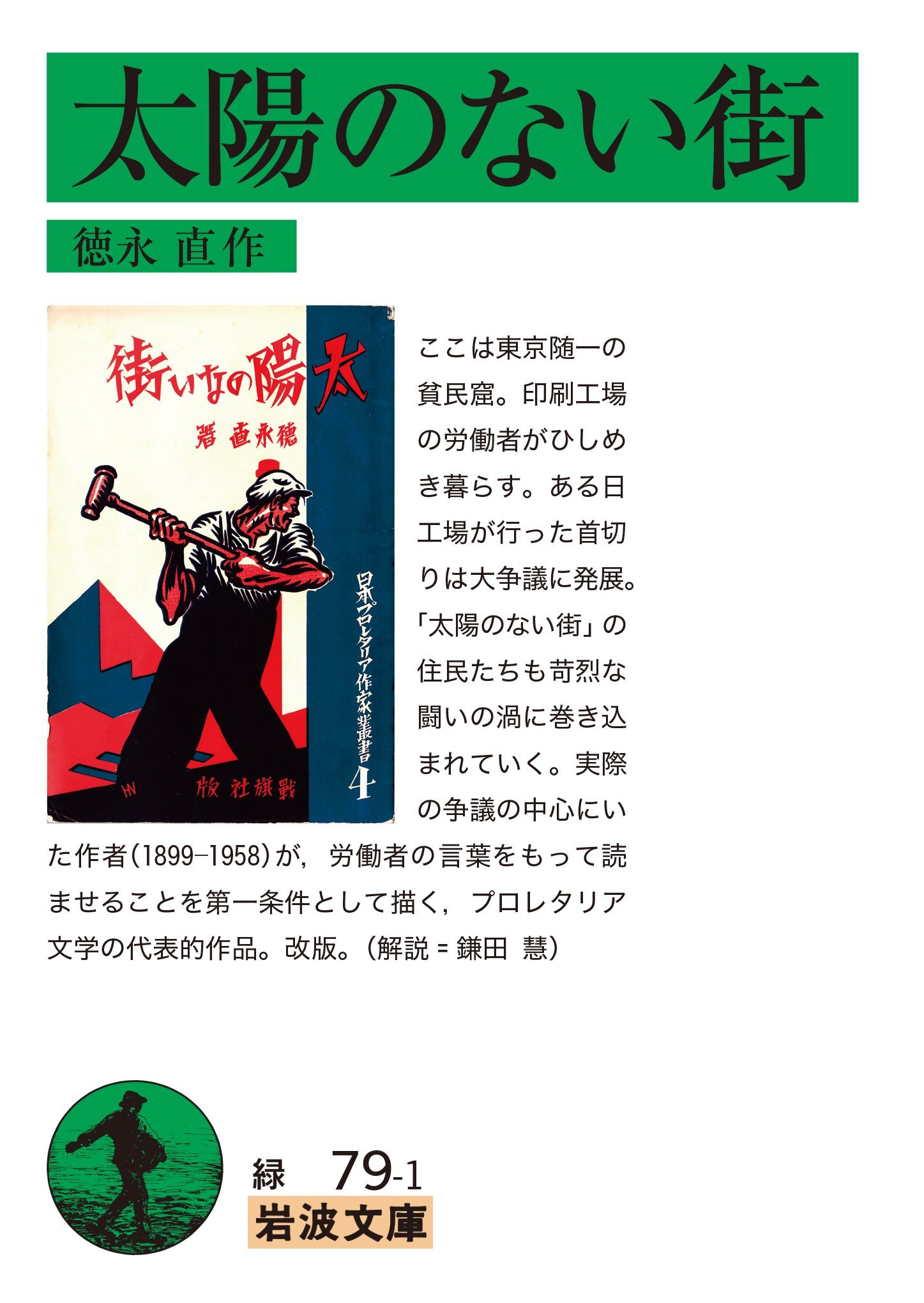|
『太陽のない街』は次のように始まっている。
電車が停まった。自動車が停まった。ーー自転車も、トラックも、サイドカーも、まっしぐらに飛んできては、次から、次へと繋がって停まった。
ーーどうした?
ーー何だ、何が起ったんだ?
密集した人々の、至極単純な顔と顔を、黄色っぽい十月の太陽が、ひどい砂埃りの中から、粗っぽくつまみ出していた。
人波は、水溜りのおたまじゃくしの群のように、後から後から押して来ては揺れうごいた。
ーー御通過だーー摂政宮殿下の高師行啓だ!
最前列の囁きは、一瞬の間に、後方へ拡がって行った。自動車は爆音をとめ、人は帽子を脱った。
冒頭の文章を読むと、この小説はこの後どんな風に展開していくのかと興味を唆られる。
『太陽のない街』は1926年に起きた共同印刷争議を題材にして書かれた小説である。争議は会社が操業短縮と賃金カットを提案したことから始まった。労働組合側は提案を拒否してストライキで対抗、以後70日間にわたって争ったが、争議は労働者側の全面的敗北で結末を迎える。
小説では共同印刷が大同印刷となり、争議団婦人部の高枝・加代姉妹と高枝の恋人で争議団幹部の萩村を中心に展開する。会社側では主に大川社長が登場、暴力団が絡む。
文庫本の解説で鎌田慧は本書を、全員解雇をめぐる大闘争がアクション映画的手法で書かれたドキュメンタリー風小説だと言っている。著者の徳永直は、誰よりも労働者に読んでもらいたいと考えたので、労働者の生活と言葉によって表現し労働者に伝えようとした。それが鎌田さんの言うアクション映画的手法、描写であった。理屈をくだくだ展開するのではなくて、場面の動きを具体的に描写する。本書冒頭の歯切れのよい描写は、読者を読み続ける気持ちにさせるだろう。
現在ではニュースに取り上げられるような大労働争議はほとんどなくなってしまった。それどころか、デモとかストとかいう言葉自体に違和感を抱くような時代になっている。しかし戦後にも三井三池争議など労使が激突する大きな争議があったし、1970年代までは交通機関のストをはじめいろいろあった。そして現在、多くの労働者は生活困窮状態に落ち込んでいる。あるいは職場を追われあるいは非正規の仕事にしかつくことが出来ない。労働者は経営側(昔の言い方をすれば資本家、要するに金、資産を持っている富裕層)に支配されている。この状況は100年前の争議を題材に書かれた『太陽のない街』の世界と共通するものがある。共同印刷争議が100年前の出来事としてでなく自分たちのことのように感じられる。
数年前に復活して読まれた小林多喜二の『蟹工船』は『太陽のない街』と同じ時期に同じ雑誌に掲載されていた。そして2作はプロレタリア文学の代表的作品と評されている。『太陽のない街』は、藤田満雄と小野宮吉の脚色により1930年に舞台上演され、戦後1954年には、映画化された。(文:宮) |