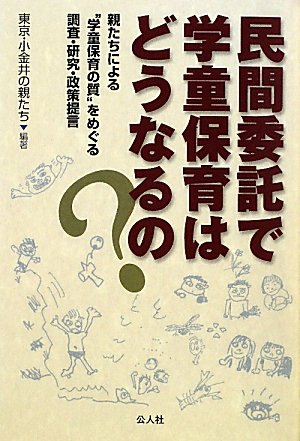|
私たちが普段食べている肉はどうやって肉になってくるのだろう?牛や豚、鶏、羊、馬の姿やかたちは知っているし、それらの肉を食べて生きてきた。主婦である私は、たまに冷蔵庫の中で腐らせてだめにしてしまうこともある…お恥ずかしい話だけれども。だけど生きて息をしていた動物のいのちをいただいているのが私たちなのだと、この本を読んだらつくづくそう思った。目の前で死んだり捌かれたりする姿を見ずに(魚はあるが)、いままで生きてきてしまった。ほとんどの場合はガラスケースの向こう側から売ってもらうか、パック詰めにされたお肉を買う。小学生の頃、通学路に豚小屋があり、たまに肉にされるためトラックにのせられて運ばれていく豚の鳴き声をきいた時のことを思い出した。牛や豚、鶏の形をした生き物を解体して私たちが普段食べるお肉にする人がいるのだよなと今さらながら思う。そういう職業が間違いなくあるのだ。
ある日「いのちのなぞ」(小社刊)の著者の越智典子さんが『ある精肉店のはなし』http://www.seinikuten-eiga.com/という映画をみたのだけれどものすごくよい映画だったと教えてくれた。この映画は大阪の精肉店を営む一家のドキュメンタリー。長いあいだ日本でもこういう仕事をする人たちに対する差別があったそうだ。でもこの精肉店の家族がとてもいい顔をしていた。自分たちの仕事に誇りもあるし、明るくて笑いもある。この家ではやって来た牛たちをしばらく自宅の牛舎で世話をし、肉にする日が来たら屠畜場へは車に載せるのではなく牛と一緒に普通の道を一緒にあるいて行く。道を牛が歩くのだから子どもたちにとっても牛は身近な存在となる。身近にそういう場所がなければ、そして大きなところでは、こういう光景はなかなか見られないだろう。
映画をみた前後、新文化を読んでいて、この本にも出会った。動物たちを捌く人がいなければ私たちは肉を食べられない。映画の中でも、この本の中でも、みんな動物たちを捌く人たちの所作は美しくて無駄がない。本には内澤さんが取材に行った時のスケッチがとても丁寧に描かれていている。屠畜は残酷か?では肉を一切食べないのか?死と引き換えに私たちは生をいただいているんだなあと思う。肉だけ見てたら考えもしなかったことだ。頭ではわかっていても。でも屠畜に関わる人たちは、動物たちに死をもたらす瞬間ですら、苦しまないようにと、なるべく一撃に近い方法をとる。いろいろな国でいろんないきものの肉が食べられているが、何が残酷で何が残酷でないのか?鯨やイルカはだめで鯛や秋刀魚や鰯ならいいのか?魚類だから?犬は?猫は?ネズミは?国によってはそういう食文化がない国もあるが、食べる行為はそれぞれの国の人が生きていく上に昔からずっと続いてきたことなのだ。肉や魚をいのちとして一切食べないで反対する人もいるだろう。いのちあるものを殺す仕事と聞いたら嫌う人もあるだろう。では草木にはいのちはないのか?と極論にならないだろうか。どれだってサイズや形が違うだけで命は命なのだ。生き物は食物連鎖でわかるように不思議な輪をつくって巡っている。いのちをいただかずに生き物は生きられないのだと思う。日本でも昔は飼っていたニワトリをごちそうにしたりした。今でも国によっては家で動物を捌いて食べる国や民族もいる。そして肉を皮を血を、骨をのこらず利用する。あますところなく。冷蔵庫がない場所や時代には必要以上には保存できなかったこともあるだろうけれど命は大切に、そして命をつなぐために活用されてきたのだと思う。今自分にできるのは目の前に肉や魚、野菜などがあれば、残さず美味しくいただくことだろうなあと思う。ああ、私はいままでなんてことをしていたのかなと反省する。肉や魚そして野菜を使いきり、おいしく食べるために調理していきたいなあと心から思った。いまだ完全にはできないのだけれど。只今絶賛努力中だ。いのちを食べることを真剣にうけとめたらみんなそんな気持ちになるのではないだろうか。そうだといいなと思う。この本には内澤さんの内面から湧き出る興味と好奇心とこの本に対する、いや食べられる動物たちへのひとかたならない愛情、この仕事をする人たちへの敬意を感じた。本との出会いに感謝。(文:やぎ) |